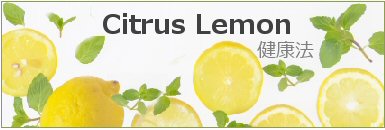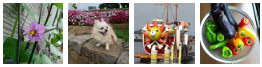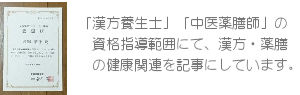TOMOIKU*ブログ
2.242017
3月3日雛祭りの由来!ひな祭りの食べ物は「親の愛情が込められた伝統的なお祝い料理」

[最新更新日:2020年2月25日:追記]
もうすぐ3月3日「ひな祭り」♪
私にとってお正月の次に忙しい日でもあります。
数年前まで、主人と息子2人の男3人と女(一応)ひとりだったので、お祝いもしないで過ごしてきた年月。
今はお嫁さんふたりと孫・私に愛犬若葉で女5人、男は義父と主人・息子2人・孫で5人と同じ人数になって、お嫁さん達と孫が華やかせてくれる「ひな祭り」になります。
華やぐ=おしゃべりがスゴイ!機関銃のようです。
数年前まで寂しかったひな祭りでしたが、息子ふたりがお嫁さんと孫を連れてきてくれて、とても素敵な日々に変わりました♪
6歳になる女の子の孫には、「ひな祭り」の由来もそろそろ話そうと思っています。
Contents
「雛祭り」「桃の節句」「上巳(じょうし)の節句」の由来
 ひな祭りは桃の咲く時期なので「桃の節句」とも呼ばれていますが、もともとは「上巳(じょうし)の節句」といって、室町時代に中国から伝わった五節句のひとつです。
ひな祭りは桃の咲く時期なので「桃の節句」とも呼ばれていますが、もともとは「上巳(じょうし)の節句」といって、室町時代に中国から伝わった五節句のひとつです。
五節句とは?
五節句で1月は1日の元日を別格とし「七草の節句」としました。
- 人日(じんじつ)の節句…1月7日・七草の節句
- 上巳(じょうし)の節句…3月3日・桃の節句
- 端午(たんご)の節句…5月5日・菖蒲の節句
- 七夕(たなばた)の節句…7月7日・笹の節句
- 重陽(ちょうよう)の節句…9月9日・菊の節句
すべて自然の草木の節句ですね。
上巳(じょうし)の節句…3月3日・桃の節句
その昔、3月上旬の巳(み)の日に、老若男女関係なく、災いを人形に移して厄払いをする「上巳節」という風習があり、身のけがれを祓い、無病息災で暮らせるようにという祈りと共に、川で身を清めて汚れを祓うという神事でした。
それが平安時代に宮中の小さな女の子たちの間で行われていたおままごとである「ひいな遊び」と合わさって、災いを人間にかわって紙人形などに移して川に流し、、女の子が健やかに成長し幸せを願ったことがひな祭りの起源だと言われています。
今でもこの風習は、鳥取や京都で「流しびな」という行事となって、旧暦の3月30日に行事として受け継がれています。
現在のように、人形を飾るようになったのは、江戸時代の徳川家康の孫娘「東福門院」が自分の娘のために男女一対の内裏びなが始まりで、名主の家庭などへ広がり、3月3日に人形を飾り「女の子の成長を祝う儀式」として定着しました。
上巳の日の頃に桃の花が咲くことから、桃には邪気を祓う力があるからとも言われています。
かわいく咲く桃の花が、甘く香りイメージが華やいでいることから女の子のお祭りとして良いとされ「桃の節句」と言われるようになったことが名の由来です。
ひな祭りの食べ物には旬の食材|親の愛情が込められた伝統的なお祝い料理
古くから伝わる伝統的な行事にはお祝い料理があって、ひな祭りには「春の訪れを伝える旬の食材」が使われています。
旬の食材を食べるしかなかった昔ではありますが、旬の食材をいただくことが、人にとっても一番栄養と環境に合わせた力があります。
そしてひな祭りは女の子の行事ということもあり、見た目もかわいく、かわいい娘への健康と幸せを祈る親心ですね。
ひし餅

「雪がとけて大地に草が芽生え、桃の花が咲く」という意味があります。
- 緑色の意味「健康や長寿」イメージは「大地」で、厄除けができる「よもぎ」は増血効果を期待。
- 白色の意味「清浄」イメージは「雪」で、白餅には「ひしの実」を加え血圧を下げる効果を期待。
- 桃色の意味「魔除け」イメージは「桃」は「クチナシの実」を加えて解毒作用を期待。
菱形で三色(緑・白・紅)のかわいい菱形は「心臓」を表していると言われていて、災厄を除いてほしいという親が娘の健康を願う気持ちが込められています。
それぞれの色にも、子どもが健やかに育ってほしいという親の願いが込められています。
雛あられ

雛あられは、もともとはひし餅をくだいて餅に砂糖を絡めて炒った、ひな祭りの節句の代表的な和菓子のひとつです。
昔はひし餅の3色だったのですが、後に四季を表すように、春桃色・夏緑色・秋黄色・冬白色と4色になり、でんぷんが多く健康に良いことから「1年中娘が幸せに過ごせるように」という願いが込められています。
その雛あられは関東はお米の形をして甘く、関西では丸くてしょっぱい感じへと、形も味も違います。
はまぐりの吸い物

はまぐりは、平安時代には女性が「貝合わせ」という遊びなどで知られ、ひな祭りの代表的な食べ物です。
はまぐりの貝殻は、対になっている貝殻でなければぴったりと合わないことから、仲の良い夫婦を表し、「夫婦和合」の象徴となりました。
女の子が将来良縁にめぐまれるように…そして、一生一人の人と添い遂げるようにという願いが込められた縁起物です。
対象の女の子にはひとつの貝に2つの身をいれてあげるそうです。
白酒

もともとは桃は邪気を祓い、気力や体力の充実をもたらすということで、桃の花びらをひたした薬酒の「桃花酒」を飲んでいました。
そして江戸時代からは、みりんに蒸した米や麹を混ぜて1カ月ほど熟成させた「白酒」の方が親しまれるようになりました。
赤穂浪士の堀部安兵衛が高田馬場の決闘前に飲み干した「どぶろく」を蒸留し、加工工程を増やし上品に仕上げたものが「白酒」です。
その後「白酒」はアルコール度数10%前後のお酒は大人しか飲めないので、子どもにはノンアルコールの「甘酒」をいただくようになりました。
ちらし寿司

ちらし寿司そのものにいわれはありませんが、れんこん-見通しがきく・えび-長生き・豆-健康でまめに働けるなど縁起のいい具材が多く使われています。
そして、春らしい華やかで祝いの席にふさわしい彩りが食卓になるので、ひな祭りの定番メニューとなりました。
現代は、ケーキに見立てたり、茶巾寿司・押し寿司・手まり寿司などのアレンジをして、さらにかわいいお雛様のお寿司になっていますね。
野菜では、芽を出すものが喜ばれ、よもぎ・わらび・木の芽などをおひたしや浅漬けにもします。
願いごとが叶うと言われるさざえや、はまぐりの代用品としてあさりなどの貝類もお料理にプラス!
桃の花を白酒に浮かしたり、子どもたちにはよもぎ餅や桜餅などでお祝いをして、春の香りがいっぱいで喜ばれます。
かわいいケーキなどのスイーツも街のあちこちにみられるようになり、春の訪れとともに街が華やかになってきますね。
ぜひ、ひな祭りならではの縁起のいいメニューを取り入れてくださいね。
<健康を意識した目的別レシピ>




生活を彩る 関連記事
* TOMOIKUの姉妹サイト紹介 *